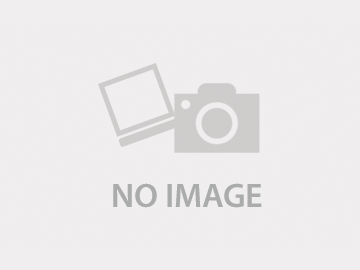「彼女の手は電話の方に伸びていた」杉良太郎が見た江利チエミの最期《死ぬほど愛した高倉健》 | ニコニコニュース
能登半島地震の被災者の避難先に物資を持って駆け付け、自ら食事も振る舞ったことが大きな話題となっている俳優で歌手の杉良太郎(79)。長年の福祉活動などを通じて、芸能界から政財官界まで幅広い人脈を築き、その知られざる人間関係については月刊「文藝春秋」の連載で語っている。
早逝した人気歌手・江利チエミとも親交が深かった。高倉健との離婚後、日ごと泥酔を繰り返していた彼女の晩年について明かした。(聞き手・構成=音部美穂・ライター)
◆◆◆
警察と一緒に不気味なほど静かな部屋に足を踏み入れると、寝室でノニ(江利チエミ)は倒れていた。ひと目見ただけで、彼女はもう息をしていないのだと悟った。体は半分以上ベッドから落ち、前の晩に食べたであろう寿司の嘔吐物がじゅうたんに広がっていて……。たった1人で死にゆく瞬間、ノニは何を思ったんだろうか。40年以上経った今も、彼女の最期を想像すればするほど、僕はやりきれない気持ちになる。
◇
長年の芸能活動と刑務所慰問・視察や被災地支援などの福祉活動を通じて、芸能の世界はもとより政官財界に幅広い人脈を築いてきた杉良太郎(79)。歌手・女優の江利チエミ(1982年没、享年45)とは、共演を通じて交流を深めた。美空ひばり、雪村いづみと「三人娘」として一世を風靡した江利。私生活では、高倉健との結婚後、経理を任せていた異父姉が江利の名義で巨額の借金をしていることが発覚。高倉に迷惑をかけまいと江利は離婚を決意。その後、江利は再婚することなく借金を1人で完済した。しかし、45歳の若さで急逝。死因は脳卒中と誤嚥だった。
◇
ノニは大先輩なんだけど、すごく気さくに接してくれた。「良さんって呼ぶから、私のことはノニって呼んで」っていうんだよ。「〜なのに」と語尾に「のに」をつけるのが口癖だったからこのニックネームがついたらしい。といっても、そう呼ぶのは、親友の美空ひばりさんと高倉健さんだけだったみたい。僕らが姉弟のように親しくしていることを、ノニはひばりさんに話していたのか、あるパーティーでひばりさんがわざわざ僕のそばに来て「杉さん、ノニがいつもお世話になっているそうで有り難うございます」とご挨拶された。これには驚いた。
心の闇に気づくことができなかった
お酒が入ると、ノニはこちらが聞いてもいないのに健さんとの思い出話をしてくれた。健さんはこだわりが強い人で、気に入った喫茶店があるといって、コーヒーを飲むためだけに往復6時間もかけて車を運転して行ったそうだ。肌着も気に入ったものがあると100枚、200枚と買ってタンスに入れておくのだとノニから聞いた。何もかもがノニにとっては魅力的だったんだろうと思う。
1982年に放送された僕の主演ドラマ『同心暁蘭之介』に、ノニが清川虹子さんと2人でゲスト出演してくれたことがある。ラストシーンで、ノニは僕に背を向けて旅立っていくんだけど、カットがかかっても聞こえないのか振り返らずに歩いて行っちゃって。清川さんと「どうしたんだろう、おかしいよね」って顔を見合わせた。
それから間もなくのこと。羽田空港でノニに遭遇したんだよ。大阪行きの飛行機に乗ったらこれまた偶然、隣の席。さらに大阪のテレビ局でもばったり会って、帰りの飛行機でも隣どうし。こんな偶然あるのかと驚いた。ノニは一晩中飲んでいたのか、お酒の匂いがして、客室乗務員にお水を何杯もお願いしていて少し心配になった。それでも、「次はどこで会うんだろうな」なんて、笑顔で冗談を飛ばしながら別れたんだ。
ノニが亡くなったのはそれから数日後のこと。彼女の友人から「チエミと連絡が取れない」と一報を受けて家に飛んで行ったら、警察が鍵を開けようとしているところだった。中に入ったら、寝室でノニは事切れていた。食べ物が喉に詰まり、苦しくて誰かを呼ぼうとしたんだろう。彼女の手は電話の方に伸びていた。
今思えば、あんなに浴びるほど酒を飲むなんて精神的によほど追い込まれていたんだろう。でも、若造だった僕は、心の闇に気づくことができなかった。そんな自分が情けなくて、ノニとの思い出を振り返るたびに胸がズキズキと痛むんだ。
ノニは、僕が自宅で開催していた寄席の常連客でもあった。この寄席は「杉友(さんゆう)寄席・恵まれない二ツ目を励ます会」といって、古今亭志ん駒さんから「落語界では二ツ目は充分な収入が得られず、芸を磨くための場所も少ない」と聞いて、僕が開催を提案したんだ。客席には俳優や政治家、スポーツ選手とそうそうたる顔ぶれがそろっていた。ノニはよく最前列に座って、目を輝かせながら落語を聴いていた。
終わった後の酒宴では、彼女は泥酔するまで飲み、よく『テネシー・ワルツ』をアカペラで歌ってくれた。あの寂しい歌声は健さんのことを思って歌っていたのだと思う。健さんが死ぬほど好きで、好きなのに別れなければならなかった。それは天国に行っても変わらなかったと思う。
◆
本記事の全文、および杉良太郎氏の連載「人生は桜吹雪」第三回は、「文藝春秋」2024年2月号と、「文藝春秋 電子版」に掲載されています。