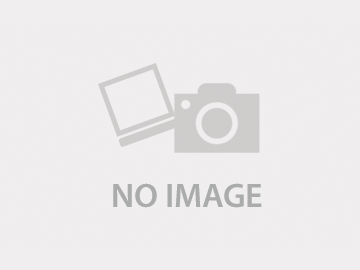7浪して53歳で医師に! 貴子先生語る「小中学校ではずっとクラス最下位でした」 | ニコニコニュース

現在、愛知県で活躍している医師の新開貴子さん(58)は、異例の経歴の持ち主だ。彼女が医師になったのは、なんと53歳のとき。まだ、5年目の医師なのだ。
そんな彼女が医師になるまでのドラマを追う(全2回の1回目)。
■「7浪して医学部に入学。53歳で医師免許を取得」
「こんにちは。お体の加減はいかがですか」
「それがね、先生。2日前に歩行器に手をかけた途端にダーッと転んでしまって、腰が痛いのよ」
1月末の月曜午後2時過ぎ。愛知県春日井市でひとり暮らしをする84歳の女性宅。要介護2で呼吸器疾患の持病もある女性は、訪問医の到着を待ちわびていたかのように、一気にしゃべり始めた。
やがて医師は、横たわる女性患者の隣にしゃがみこむと、
「めまいはどうですか」
「やっぱり立ち上がるときが、いかん。でも、今日はめまいも腰も少しラクになって、大好きなラーメンを食べられたよ」
「寒い日は、あったかいラーメンがおいしいですよね」
聴診器を胸や背に当てる間も、会話を途切れさせることなく診察するのは、医師の新開貴子さん(58)。今日も所属する同市の勝川よろずクリニックから、看護師とふたりで車で20分かけて在宅診療にやってきた。女性患者の顔から当初の不安げな表情は消え、笑顔で続ける。
「診察もていねいだし、何でも話せる貴子先生が大好きだよ」
その後も、血圧測定や服薬の指示など1時間弱の診察を続け、
「また来ますからね。お大事にしてください」
往診用のカバンを手に車まで向かいながら、貴子先生が言う。
「私が話しやすいというのは、きっと娘さんと同世代だからでしょう。私自身も、自分の母親と会話するような気持ちで向き合っています。今日のように、患者さんが元気になる姿に接するたびに、ああ、医師になってよかったと思うんです」
快活な口調で話す貴子先生は、異色の経歴の持ち主だ。58歳にして、まだ医師歴5年というキャリアが、その事実を物語る。
医師を目指したのが32歳のとき。その後、7浪して40歳で医学生となり、3人の子供を育てながら、53歳で医師免許を取得した。当時をふり返って言う。
「小中学校を通して成績もずっとクラス最下位だった自分が、まさかお医者さんになるなんて、夢にも思っていませんでした」
意外にも、少女時代の貴子先生は、「劣等感と孤独感のかたまり」だったというのだ。
■「劣等生だった小学校時代。東京での生活に疲れ、郷里に戻り……」
「物心ついたときには、母がクラブや薬局を経営していて、すごく繁盛させていました。父はもともとバーテンダーで、その後は母の仕事を手伝ったりしていました」
1965年(昭和40年)3月17日、島根県松江市に生まれた貴子さん。
「自宅1階がクラブで、その2階が私たちの住居でしたが、両親はいつも不在で、私と2つ年上の兄は生後3カ月から近所に住む子守りのおばあさんに育てられ、しつけもしてもらいました」
「まわりは親が大学教授や医師など教育熱心なご家庭ばかりのなか、うちは勉強に集中できるような環境ではなかった。『水商売の家の子と付き合うな』と親から言われてる同級生もいて、私はつらくて、母に『クラブをやめてくれ』と訴えたことも。先生からもほったらかしの私は、クラス42人中41番目か42番の成績で、もうひとりの男子といつもビリを争ってましたね」
家庭にも学校にも居場所がなかった。
「劣等感と孤独に苦しみ、4歳ごろから始まった自分の毛を抜くクセがずっと続いてました。のちに抜毛症という病気だと知るんですが。きっと、母が夜もいなくて寂しかったんでしょう」
中学卒業後は周囲の同級生たちが進学校に進むなか、「偏差値が足りず」に私立の女子高へ入学。両親の離婚は、その直後だった。
「母は家にはおらず、父も外に女の人がいたりで常に両親はいがみ合っていたので、娘の私でも、離婚は当然の結末と思いました。高校を出ると、地元での暗い生活を何とか断ち切りたいと思って、上京します。とにかく、あの家から、島根から出たかった」
東京女学館短期大学では、かろうじて好きだった英語を専攻した。
「まわりはお嬢さんだらけで自家用車での送り迎えもあるなか、たぶん自転車通学は私だけ」
家賃9千円のアパート、弁当販売店でのバイトなど苦学生の生活だったが、家族の煩わしさから解放されて充実した毎日だった。
卒業後は東京でレナウンの海外事業部に就職し、3年後には日本航空に転職して羽田空港でグランドホステスとして勤務する。
「大好きな高倉健さんのチェックインを3回ほど担当したのは、忘れられない思い出です」
しかし、短大を出て社会人になって、順調に過ごしているように見えるが、実際は違っていた。
「もう上京してすぐから、拒食と過食を繰り返す摂食障害が始まっていました。一時は、体重も一気に15キロくらい落ちてしまって」
心身に限界を感じ、帰郷を決意した。そして、
「摂食障害になったり、人間関係をうまく築けない自分の心の空洞の正体を知るために、心理学を学ぼう」
そう思い、26歳のときに島根大学教育学部にAO入試(総合型選抜)で入学。以降、実家の薬局を手伝いながら、臨床心理士を目指した。
「勉強を続けるなかで、私の根っこには“母に見捨てられた”という消化できないままの感情があると、改めてわかってきました」
座学に加えて、2年間にわたりアルコール障害や摂食障害のセルフミーティングに関わるなかで、ある思いに至る。
「私の理想とする医療をやろうと思ったら、自分自身が決定的な判断を下せる立場にならなければできないのではないか、と。そのとき初めて、医師になりたい、という思いが芽生えました」
32歳の決心を「応援するよ」と誰より喜んでくれたのが、父親の邦洋さんだった。当時、邦洋さんは近所で中華料理店を営んでいた。
しかし、そのわずか半年後の1997年9月半ば、貴子さんは顔見知りの酒店店主から、父の店が2日間も閉まったままだと聞かされる。
「胸騒ぎを覚え合鍵で店に入ると、父が倒れていました。救急車を呼びましたが、私は意外に冷静で、もうダメだなと思っていました。60代半ばだった父は持病の糖尿病があったうえに酒浸りだったし、なにより私や家族と離れて、ひとりで暮らす寂しさも大きかったのでしょう」
そして、貴子さんは思う。
「お父さんが苦しんでいるのに、私は何もしてあげられなかった。父のように病に苦しみ、自ら死を選ぶ人を救いたい。患者さんに寄り添い、体も心も支えたい」
医学部受験のため、最初に始めたのは、中学の数学からやり直すことだった。
(取材・文/堀ノ内雅一)
【後編】7浪して医学部、国会試験に2回落ちて53歳で医師になった女性「それでも諦めなかった理由」へ続く