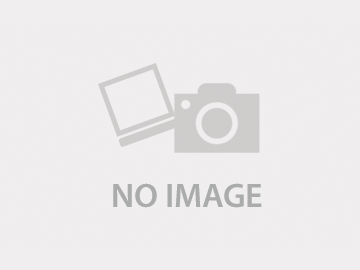いったいどんな業界が日本進出を図っているのか。そして、どんな業界で韓国企業が規模を拡大しているのか。分野別に見ていこう。
まずは消費者に身近な食品分野から。韓国の即席麺市場は、辛ラーメンで知られる農心が1位で、2位は三養(サムヤン)食品、3位はジンラーメンを販売するオットギで、ヤクルトグループの八道(パルド)などが続いている。
2019年1月、そんな業界2番手の三養食品が日本法人を設立した。オットギに2位の座を奪われそうになった2012年、激辛の「ブルダックシリーズ」を発売した企業である。
当初はあまりの辛さから敬遠されたが「ブルダックを食べてみた」という動画をアップするユーチューバーが次々と現れて、世界累計20億食を超えるヒット商品となった。
辛さの基準のスコビル指数(SHU)は、辛ラーメンの2700SHUに対して最も辛い「ヘクブルダック炒め麺」は10000SHU。辛さに自信がある御仁はチャレンジしてみてはいかがだろう。
そんな同社のホームページには、日本の明星食品の技術支援を受けて開発したと記載されている。
もちろん、農心も日本の食品会社から技術支援を受けたし、オットギも同様だろう。食品に限らず、日本の技術支援を受けた韓国企業は少なくないが、公表している企業は珍しい。会社全体では2000億ウォン(約200億円)を輸出したなか、36億9000万ウォンと輸出額全体の1.8%余りにとどまった日本に同社第1号の海外法人を設立している。“地元”企業の支援を受けながら、日本市場での規模拡大を図っているのだ。
また、焼酎も成功といってよいだろう。眞露(現・ハイト眞露)は1979年に日本で甲類焼酎「JINRO」を発売し、斗山(2009年に酒類事業をロッテへ売却)も1996年から「鏡月」の販売を開始した。
いまとなっては「鏡月」は韓国焼酎だと知らない人もいるほど日本国内で普及しているが、「JINRO」と「鏡月」は韓国では販売していない輸出商品である。
さらに、化粧品業界でも韓国コスメの人気は広がっている。韓国化粧品大手のアモーレパシフィックやミシャが早くから日本に進出しており、中堅化粧品会社のAN (エイエヌ)も日本進出を進めている。
韓国・忠清北道で産出されるイライトを主原料にエステティックサロンや美容院向け化粧品を製造しているANは、ウィズコロナに転換した今夏、日本市場を視察し、9月には東京ビッグサイトで開催された展示会「ダイエット&ビューティーフェア」に初出展した。
韓国コスメは関税が免除されていて価格の面でも競争力がある。ANは展示会で十分な手応えを感じたという。
連敗続きの業界も…? 韓国大手企業の悲喜こもごも
一方で、必ずしも進出した業界で全て順調にシェアを広げられているわけではない。
たとえば、飲食チェーンのBBQ Chickenやソルビンなども、進出したものの成功とはほど遠い。
韓国のフライドチキンはアジア各国で人気がある。しかし、日本KFC(ケンタッキー・フライド・チキン)の味に慣れ親しんだ日本人には受け入れられなかった。また、ソルビンはさらりとしたかき氷で韓国に加えて中国でも人気を得たが、その独特の食感はそもそも日本製かき氷機が作り出す食感であり、日本では特に目新しさはなかった。
さらに、同じ酒類でも明暗が分かれている。焼酎に比して韓国ビールは日本ではほとんど知られていない。理由は味だ。
ハイト眞露の「ハイト」とOBビールの「カス」はコクがなく、焼酎と混ぜて飲む韓国人も少なくない。韓国語で焼酎を意味する「ソジュ」とビールを意味する「メクチュ」の頭文字を組み合わせて「ソメク」と呼ばれている。
実際、韓国市場でも日本のビールのコクは浸透しつつあり、2013年、韓国の商工団体が日本製品不買運動を提唱した際、「韓国ビールよりアサヒビールを飲みたい」という理由から拒絶した人が続出したのが不発に終わった一因と囁かれた。いわんや、その“本場”である日本では勝負にならない。
結果として、その余波は韓国ビール全体の不人気として浮かび上がっている。近年最も大規模な不買運動となった2019年の不買運動の際には70%の韓国人が参加を表明したが、日本ビールの代りに選ばれたのは、韓国のビールではなく、青島やオランダ・ハイネケン、ベルギー・ステラアウトワなどだった。
こうした逆境を見た各社は、新製品の開発と販売に取り組んだ。ロッテ酒類は日本ビールをベンチマークして2015年に発売した「クラウド」の販売を強化した。ハイト眞露は「テラ」、OBビールも「ハンマック」を開発。各社、輸出も視野に反転攻勢の機会をうかがっているという。
諦めない韓国企業の「チャレンジ」合戦
苦戦が続く業界のこうしためげぬ「チャレンジ」は、何もビール業界だけの話ではない。
たとえば、今夏、現代自動車が日本で燃料電池乗用車の販売を開始した。現代自動車は2000年に日本法人を設立し、2001年から乗用車の販売を開始したものの売上不振によって2010年に日本の乗用車事業から撤退している。それから10年以上が経った今年7月、電気自動車のアイオニック5と燃料電池車のネッソの販売を開始したのだ。
1998年にサムスンから独立したネイバーは、2000年に日本語サービスを始めたが、2005年に撤退を余儀なくされた。その後、2007年に再上陸して「ネイバーまとめ」を開始し、ライブドアを買収したが、決め手にかけていた。
ネイバーに転機が訪れたのは2011年3月だ。東日本大震災の直後に東京に出張した李海珍会長は、被災者がSNSで家族や親戚と連絡を取ろうとする姿を目の当たりにした。そこで、韓国で普及していたカカオトークを参照して「ネイバーLINE」を開発した。
「LINE」は本社を東京に置き、李会長自ら東京に滞在して開発の陣頭指揮を取った。
ネイバーが開発したLINEは韓国でも知られているが、使っているのは在韓日本人か日本と接点がある人くらいで、日常的に使っている韓国人はほとんどいない。韓国よりむしろ日本で成功した事例である。
なぜ韓国企業は日本市場を目指すのか
なぜ、必ずしも成功するわけでもない日本市場に、韓国企業が何度もトライするのか。
韓国企業が日本進出を目論む理由は主に3つある。
1つ目は市場規模だ。韓国は人口5000万人で、日本は1億2000万人。韓国市場は飽和状態になりやすく、早い段階から海外に目を向けてきた。
そもそも、韓国市場は多くの分野で大手1社か2社が独占しており新規参入は難しい。自動車は現代と起亜、家電はサムスンとLG、百貨店とスーパーは新世界とロッテがシェアを二分する。
身近なところでもカフェは新世界グループが運営するスターバックスとロッテグループのエンジェル・イン・アスが市場を抑えている。上述の即席麺は一人勝ちの農心を他メーカーが追いかける構図となっている。
そうした「閉鎖的」な韓国市場と比べ、日本市場は新規参入が容易で、なおかつ全体の市場規模が韓国よりも大きいため、ニッチな市場も十分な大きさで形成されている。
2つ目の理由は先進国など第三国への足掛かりだ。現代自動車が日本で販売を開始した燃料電池車は、トヨタと現代が世界市場を二分する。日本市場では“お膝元”であるトヨタの足元にも及ばないだろうことは想像できるが、一方、米国や欧州、アジアでの販売を見据えたとき、同じ東アジアのライバルとの比較は欠かせない。その比較データの収集が容易な市場が日本なのだ。
最後は、「日本製」という表記だ。上述のANは、当面は代理店を通して輸出したい考えだが、将来的には日本に製造拠点を置く可能性もあるという。韓国コスメは日本では人気があるので韓国製で問題ないが、中国市場は違っている。
近年、日本に製造拠点を置く中国企業が増えている。中国では同じ製品でも中国製より韓国製、韓国製より日本製が高く売れるため、日本に工場を作ったり、OEM先を探したりする中国企業が増えているのだ。同じように中国向け製品を日本で作ろうと考える韓国企業も現れているという。
コロナ禍で途絶えていた往来が戻る中で…
こうした企業進出は、じつは日本から韓国への向きでも動きが進んでいる。
サムスンや現代、LG、SKハイニックスなど韓国のグローバル企業に部品や素材を供給する会社は、日本政府が韓国を輸出管理のグループA、いわゆるホワイト国から除外して以降、韓国向け輸出に時間がかかるようになった。韓国企業に納入する素材や部品の製造拠点を韓国内に置く例が相次いでいる。
欧米市場への進出は日本が豊富な経験を持っているが、ベトナムなどの新興市場は韓国企業が豊富な経験を持っている。短期間で成長を遂げた韓国は新興市場に進出する練習にもなるだろう。
韓国内の日本製品不買運動は事実上終焉し、コロナ禍で途絶えていた往来も回復の兆しを見せている。こうした中で、日韓双方の企業の、互いの市場をうかがう状況も再開し活発化する兆しを見せているのだ。
(佐々木 和義)