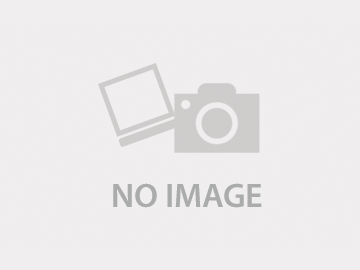そんな眞栄田さんに、本作の印象や撮影時のエピソードに始まり、役柄通り何でもこなしてしまうように映る一方、思いがけない挫折を味わった過去を直撃。俳優デビュー当時は、「勝手に進められたという反発もあって、正直、最初は嫌でした」と、率直な胸の内を明かしてくれました。
デビューのきっかけを作った映画の監督
――本作の監督である羽住英一郎監督の『OVER DRIVE』の試写会に行った際に、業界関係者から声をかけられたことが、俳優デビューへのきっかけに繋がったそうですね。
眞栄田郷敦(以下、眞栄田):はい。そこでご縁があって。その時は羽住監督とはほとんどお話していないのですが、『カラダ探し』もそうなんですけど、『OVER DRIVE』も日本っぽくないテイストの映画で、とても印象に残っていました。今回、こうして仕事について少しわかってきた時期にご一緒できることになって、めっちゃ気合が入りました。
――ホラー作品初挑戦で、共演も初の方が多いですね。
眞栄田:橋本さんは『午前0時、キスしに来てよ』以来2度目の共演ですが、ほかの方は初めてでした。僕、めっちゃ人見知りなんです。舞香さんがすごくフランクで、「入りなよ」みたいな感じで接してくれるので、すごく助けてもらいましたし、みんな本当に仲良しになりました。
最初は飽きられるかなと不安も
――主人公たちが死を繰り返しながら、解決策を探り、その過程で絆が生まれていくという、ユニークで斬新な設定のホラーです。
眞栄田:展開は違うかもしれないけど、同じ日を繰り返すということで第一印象では、観客が飽きてしまうんじゃないかと思ったんです。でも、映像で観ると、ちょうどいいところで挿入歌が入ってテンションが上がったり、人間模様が変化して青春になっていく感じのバランスも良くて、最初に自分が抱いた印象とは違いました。完成した作品を観たら、すごく良くて。素直に「めっちゃ面白かった~」と思いました。
自分は友達に相談事はしない
――ザ・青春といったシーンも多いです。撮影現場でもそうした青春感はありましたか?
眞栄田:めちゃくちゃありました。本当に楽しかったんです。海のシーンとか。濡れたらいけないからって、念のためにってマイクを外してたんですけど、結局、男3人、海にドボーンとなって。ほんと、「青春してるなー」と思いました。走るのもすげー楽しくて。みんなで座って並んで夕陽を見ながらしゃべったりして、6人の関係性が撮影をしているなかでできていたので、心から楽しかったです。
――6人は抱えていたものを吐露していきます。眞栄田さん自身は怒りや悲しみを友達に相談しますか?
眞栄田:しないです。全く。相談してもしょうがないと思うし。自分で我慢すればいいことは我慢するし、仕事でうまくいかないとかそういうのは、もう自分でやるしかないから。相談とかはしないです。
橋本環奈との再共演。「成長した」と言える
――モチベーションが下がったときは?
眞栄田:「できねー、自分」というのもモチベーションになります。悔しいままなのは嫌なので、そこで辞めるという選択肢はないですね。特に仕事は。この仕事をやっていくと決めた以上、明日は来るし、現場は進んでいくから(気分が)落ちていてもしょうがないですよね。
――負けず嫌いですか?
眞栄田:ですね。ほかの人と比べてどうのというのもありますが、それよりも自分自身に対して、負けず嫌いというのが大きいです。たとえば、デビュー直後に環奈さんと共演して、そこから2年ぐらい経っての再共演になりましたが、あの時点から「自分は変わったのか、成長したのか」と聞かれたら、絶対に「成長してる」と言えます。それが言えないようなら、すごく落ち込むでしょうね。
サックス奏者から芝居の道へ
――眞栄田さんは、プロのサックス奏者を目指していたとか。そこからお芝居の道に転換したわけですが、当時、挫折感もありましたか?
眞栄田:めちゃくちゃありました。僕は本当に音楽しかやってこなかったので。大学への受験に失敗して、「この先、本当にどうしよう」という感じでした。
――ちょうどそのタイミングに俳優への声がかかったそうですが、タイミングがずれていたら、浪人してサックスを続けていたかも?
眞栄田:高校生のときに芝居のお話をいただいていたら、絶対にやってなかったですし、逆にもっと先だったとしても、サックスをもう1年頑張ってみようとなっていた可能性があります。(受験に)落ちたその春に声をかけていただいたので、本当にタイミングですよね。父親(千葉真一)が導いてくれて、環境を作ってくれました。ただ、最初は迷っていたんです。中途半端なことはしたくないので。
最初は「勝手に進められた」と反発も
――そうだったんですね。
眞栄田:正直、最初は嫌でした。勝手に進められたという反発もあったんです。でも今振り返ってみると、すごく有難いことで、10年近く楽器だけをやってきて、そこから全く違う道に進む選択をするのは、自分では絶対に無理でした。とにかく「一度本読みを」と言われて、やってみたときにできなくて、悔しさを知って、魅力も知って、同世代で芝居をしている人たちの凄さもわかって、どんどんこの仕事に引き込まれていきました。
――実際にお仕事をするようになって、大切にしている信念はありますか?
眞栄田:自分だけじゃできない仕事です。映画もドラマも、人と人との関わりがあってできるものだから、そこは一番大事にしたいと思っています。挨拶や感謝といったことは当たり前だとして、作品に携わらせていただく以上、100%全力で向き合いたい。それができていないと絶対に分かってしまうし、逆に、向き合っていることも伝わると思うんです。だから、人と作っているということを忘れずに、感謝の気持ちとこだわりを持って仕事をしていきたいです。
ルーティーンもゲン担ぎもない

――本作はループものですが、眞栄田さんは、毎日のルーティーンや、ルール、ゲン担ぎのようなものはありますか?
眞栄田:ルーティーンもゲン担ぎもないです。ゲン担ぎとかって、それがダメだったときに何とも言えない気持ちになるし、そういうものに頼りたくないんです。ルールは……やっぱり現場の人を大事にするってことかな。
――最後に、読者におすすめメッセージをお願いします。
眞栄田:みなさんも、人間関係とか、日々大変なことがあると思います。この映画はホラーですけど、そういう悩みもすごくリアルに描かれています。モヤモヤを抱えた6人が集まって、カラダ探しを通じてかけがえのない存在になっていく。ヒューマンストーリーとか、青春感のバランスもすごくよくて、観終わって単純に「面白かった!」と言える映画だと思います。エンターテインメントとして、気軽に楽しんでください。
<取材・文・撮影/望月ふみ>
【望月ふみ】
ケーブルテレビガイド誌の編集を経てフリーランスに。映画周辺のインタビュー取材を軸に、テレビドラマや芝居など、エンタメ系の記事を雑誌やWEBに執筆している。親類縁者で唯一の映画好きとして育った突然変異 Twitter:@mochi_fumi