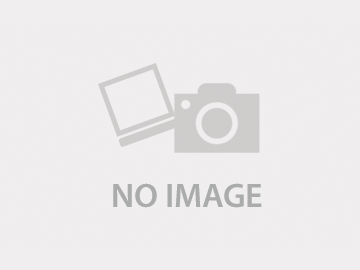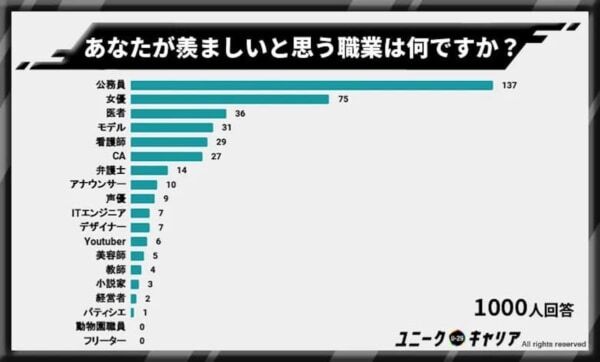〈告白〉「契約取れなきゃ3年目には給与9000円って人も…」厳しすぎるノルマに追いやれられた保険外交員がとった“衝撃の行動” | ニコニコニュース
「いいねぇ。若いねぇ。ふぅん、へぇ」と品定めの目を向けられて…新卒で大手保険会社に就職した女性(28)が明かした“枕営業”のリアル から続く
就活に疲れ果てた若者がたどり着いたのは保険の世界。就職前は、洗練された大人な女性保険外交員に憧れていたものの、いざ入社してみると、あまりにも過酷な現実が待ち受けていた……。そんな保険業界での厳しい現実と、その中で生き抜く苦悩をまとめた一冊が、忍足みかん氏による『気がつけば生保レディで地獄みた。』(古書みつけ)だ。
ここでは同書の一部を抜粋。恐るべきノルマの実態、そして、ノルマに追い詰められた女性がとって驚きの行動について紹介する。(全2回の2回目/前編を読む)
◆◆◆
「あ、先生、お久しぶりです! 三上です~。今度よかったら」
残る友人や知人で保険の話を聞いてくれそうな人に片っ端からアポを取り、保険を勧めていく。
休職を挟んだ期間に私からの「お茶しよ」「イベント来ない?」の連絡がなかったから、皆、私が保険屋を辞めたと思っていたらしく、警戒されずに会えた。すんなりとアポが取れると、『赤ずきん』に出てくる狼のように、自分がこずるい生き物になってしまった気がした。とはいえ、こずるい上等、だと何食わぬ顔で会っては保険を勧めた。
社会人を2年もやってると、会社に保険屋が出入りするせいか、交わし方を身に付けてきている。
「あのね、言ってなかったけど、私の叔母が保険屋さんだから、保険はその人に全部任せてるんだ」
「え? そうなの? どこの会社って聞いてもいい?」
「えーっとジャパン生命……」
職域での縄張り争いのように、私たちには身内が保険屋の場合、手を出せない…という暗黙の了解があった。
身内に保険屋がいる=縄張りよりもさらに手が出せない、もはや神域だ。
それを知っているのかわからないが、以前はそんなこと言っていなかったのに、皆、口を揃えて「叔母が」「いとこが」と言うようになっていた。嘘か本当かわからない。しかし、言われたらもう無条件に引くしかない。どうしよう。
そんなとき、とある友だちに会った。
中学校時代の同級生の彼女は、派遣で働いているから保険屋との接点はなく、「叔母が」「いとこが」の盾にかわされることはなかった。
「保険かぁ……入りたいけど、手取り安いから、この金額は無理かなぁ」
「5000円でも高い……かな?」
「うん。でも、乳がんかぁ……若くてもなるって言うよね? この前、元アイドルの子も20代でなったってニュースで見たし、気にはなるけどなぁ……。もうちょいお金に余裕があればなぁ」
「お金……かぁ」
「派遣だからねぇ、やっぱ給与がね。もうギリギリだよ。男性の正社員と比べると絶望的。自炊するけど、安い店必死に駆け回ってる」
「わかる……もやし最強だよね」
「そんなわけないじゃん! 保険取れなきゃ、3年目には給与9000円って人もいるんだよ」
「へ? バイトの日給じゃなくて?」
「まさかの正社員の月給」
「もし、お金を気にしなくていいなら入るんだけどねぇ」
「保険料を肩代わりすれば……」頭をよぎった危険な考え
保険料立て替えという罪は、立て替えた分のお金を返してもらってチャラにできた気でいたが、やはり償っていないので、罪はいつまでたっても罪として、私の中に残っている。保険に入りたいという意思はあるけれど、金銭的に余裕がないという友人を前にしたとき、それが疼いた。
この仕事をしてきた経験上、保険に率先して入りたいという人は少ない。保険に入りたいけれど、金銭的理由が邪魔をして入れない人なんて、なかなか出会えない。
ビンゴが始まるや否や、皆「真ん中が三上かぁ」と嘆きつつも、続々と契約を積み上げた。
そしてもう、NJ(編集部注:会社から指定されているノルマ。ノーマル実働の略)を達成した人もいた。達成者の名前の上には、紙で作られたピンクの花がつけられる。「三上」という名前の周りに少しずつ花が咲き始めた。私以外が咲き誇り、いたたまれなくなる日も近いだろう。そうさせないためにも、私も花に水をやらねばならない。こんな人、逃しちゃいけない気がした。
保険に入るのに障害があるのであれば、それを私がどうにかしてあげる、岩ならば砕くし、獣が立ちはだかっているのならば狩ってあげる。追い詰められる日々によって、悪い意味での死に物狂いの精神だった。この獲物を逃すものかと、私の口はすんなりと、とんでもない言葉を口にした。
「お金のことなら気にしないで」
「え?」
「私が出すよ」
「え、でも、みかんも大変なんじゃ」
「ううん、私はまだ保障給があるの! だからさすがに9000円はないからさ」
保障給は、本当は雀の涙ほどしかない。手放すのが惜しい。生きていくのに必要なお金。意志に反して口が動いた。
「気にしないで! ほんとに。がんとか怖いし、入っておいて損はないでしょ!」
「う、うん。じゃあ、余裕ができるまでお願いしても……いい……?」
マサ(編集部注:筆者の小学校の同級生。戸籍はまだ女性だが心は男性)の保険料を肩代わりしたときにふと、「こういうやり方をすれば保険に入ってくれるのではないか」という魔が差した考えが浮かんで、「いけない、それは違反だろう」と自分を諫めたことがある。あれが伏線になってしまった。
「本当にいいの」
「うん、もちろん」
「払おうか?」という無敵の呪文を手放せなくなった
どんどん暴走していく。「払おうか?」は、無敵な呪文になった。その言葉さえ言えば契約が取れる。お金がネックで保険に入るか躊躇う人に出会うと、その呪文を唱えた。
土日のサービス出勤、サービス残業、ウザがられる家への訪問や投函、自腹を切ったプレゼントをしても、契約が取れなかったのに、この呪文を唱えるとあっさりと契約が取れる。おもしろいくらいだった。
何か振り切ってしまった感がある。悪いことをしているのはわかっているけれど、ただ、本当に契約が欲しかった。一つでも多くの契約が欲しくてたまらなかった。まともに、真面目にやっては契約なんてそう簡単に取れない。パンプスの中を血豆で赤く染めて、絆創膏を2枚重ねづけするものの、痛みは拭えずに担当地域を裸足でヨロヨロ歩いたり、嫌われたり、友だちを失ったり、拒まれ続けた私はもう限界をとっくに超えていた。
契約を積むにはもう手段など選んでいられない。私は止まれなかった。
契約の取り方なんてどうでもいい……とにかく契約があればいい、契約があれば安心する。
ビンゴの紙の「三上」という苗字の上にようやく咲いた花、営業成績一覧に積まれた契約を見ながら胸を撫でおろす。思わず笑いそうになった。それも立っていられなくなるような、笑い。まるで漫画のワンシーンのように、床を転がり、大声を上げて笑い出すような。さすがにオフィスでそれはできないから、こっそりとあのアイデアコンテストの結果を片手に涙した非常階段へ行き、そこで鉄柵をグッと握って風を受け、空を仰ぎながら、笑った。
「アハハハハ、契約取れてる! 取れてる~」
何がおもしろいかはわからなかった。とにかく笑えて仕方がなかった。ビンゴは達成し、11月戦を無事に終えた。その時点で、呪文を使うのはやめるべきだった。けれど……。
「ふざけんなよ、どうなってんだよ、この数字。上に立つおまえがしっかりしていないからこんなちんけな数字しか上げられないんだろう。しっかりしろよ!」
オフィス長を怒鳴る支社のトップの老年男性の声を思い出す。怒鳴られるオフィス長や委縮するマスターらの姿も見たくなかった。血がつながっているわけではないが、毎日顔を合わせているオフィス長やマスターが、働きアリを管理するだけの、現場にも出てこないような男性に言葉と声量でいたぶられているのを見ると、DVを目の当たりにした子どもみたいな気持ちになる。なんとかしなくては。悪からオフィスを守るような気持ちで呪文を唱え続けた。
「やればできるって思ってたよ」周囲からの賞賛と罪悪感
今までは契約ゼロの月もあった。延命してからはゼロの月などない。それもそのはずで、正しい契約の取り方ではないのだから。とはいえ、契約ゼロのいたたまれなさや惨めさに比べたら、いけないことをしているという罪悪感すら薄らいだ。もう感覚が麻痺しているのだ。契約を取れるのならば、あとのことはどうでもいい、どうにでもなればいい。明るい自暴自棄のような状態が数か月にわたりずっと続いていた。
そんなある日。
「三上、最近、契約取れてきてるね」
テレアポ中に、マスターからふいにそう言われてドキリとする。
「いえ、そんなことは」
実力で、正しいやり方で契約を上げていると疑わないマスターの言葉には、申し訳ない気持ちで久しぶりに胸が痛む。初めて罪悪感を知ったときみたいに胸の痛みを感じ、思わずよろめきそうになる。
「やればできるって思ってたよ」
もしこれが自分の実力で契約を上げているのならば、胸を張って誇ってよいかもしれないが、私は誇れることなどしていない。むしろ、咎められることしかしていないのに……。とてもとても心が痛んだ。痛がる資格なんてないのに。
「これあげる。お客さんのところでもらったの。シルバーに上がってからずっとがんばっているから、そのご褒美だぞ」
「いえ、あの……」
こんなのもらえない。だって私は……。
「本当に偉いよ。私なんてこのままじゃブロ落ちだもんなぁ、がんばらなくちゃ」
「いえ、ルミさん……そんなことなくて」
「……これ、ハピ郎のティッシュ、新作だから使いなよ。意外と根性あったね、三上って」
ルミさんや緒方さんからもそう言われて、いたたまれない。この人たちは私が違反を起こしていることを知ったらどんな反応をするのだろうか……。今すぐに、「実は私!」と言ってしまおうかとも思った。当然、そんなことはできない。
「私より年下なのに本当にすごいなぁ」
「めちゃくちゃ憧れちゃいます」
中途採用の年上の後輩さんや、今年、新卒で入ってきた後輩にキラキラとした眼差しを向けられて、申し訳なくなる。憧れられるような人間じゃないよ。本当はね、偽物なの、嘘ばっかりなの。有村さんもこんな気持ちだったのだろうか。
憧れるのは簡単で、ただ胸の高鳴りに身を任せていればいい。一方で、憧れられるというのはうれしい反面、憧れに相応しい自分でないと重くてつぶれてしまいそうになる。
気がつけば抜け出せない蟻地獄
「三上さん、あと1件の契約で次の職選、ゴールドだよ」
オフィス長の一言で皆が、「すごい」と沸いてくれるものの、もう心臓は止まりそうだった。
ゴールドに上がれるのはうれしい。この先、契約が取れなくても、少なくともシルバー落ち、ブロンズ落ち、したとしてでも、ここにいられるわけだから。けれど、こんなことずっと続けられるのだろうか……。その不安は前からあったにもかかわらず無視をしてきた。ここにいる限り契約を取り続けなくてはいけない。私は本当にこのまま進んで大丈夫なのだろうか。
「最近、がんばってるもんね」
本来ならば場の主役になって賞賛されて、賞賛の言葉一つひとつを花のように一輪一輪愛でて、花束のように抱きしめたかった。現実、私はその賞賛の言葉を受けるような立場ではないから、「がんばっている」「よかったね」の優しい言葉は、ナイフのように体に刺さって、その刺さったところから垂れ流される血が、ようやく私に善悪の感覚をジワジワと戻させる。
我に返ると、私ったら何をしていたのだろう……と恐ろしくなった。いくら恐ろしくなったところで、保険料を肩代わりした契約が消えるわけではない。
「あの、オフィス長」
「ん?」
「えっと、あの……なんでもないです。すみません」
罪悪感に耐えられなくなり、罪を告白しようとした。
言えなかった。
今までの私、どうかしてた、今日からは心を入れ替えてやろう! もう取ってしまった契約はバレないように守っていく。もうあの呪文は使わない。そう心を入れ替えて出勤し、アポに向かうものの、真面目にやってもやはり契約は取れないのだ。いつもの何倍も足を動かしているのに、ちゃんとした契約が取れないのだ。
同時に、肩代わりすると宣言した保険料が生活を圧迫している。
魔法の言葉は確かにその場では魔法のように契約が取れるけれど、当然保険料は発生し、のしかかる。肩代わりした金額が給与とたいして変わらない額になり、保険料の足しにしようと始めた夜のカラオケ店のバイトで酔っ払いにくだを巻かれて絡まれて、ヒットポイントが削られる。
恐ろしいまでの自転車操業だった。