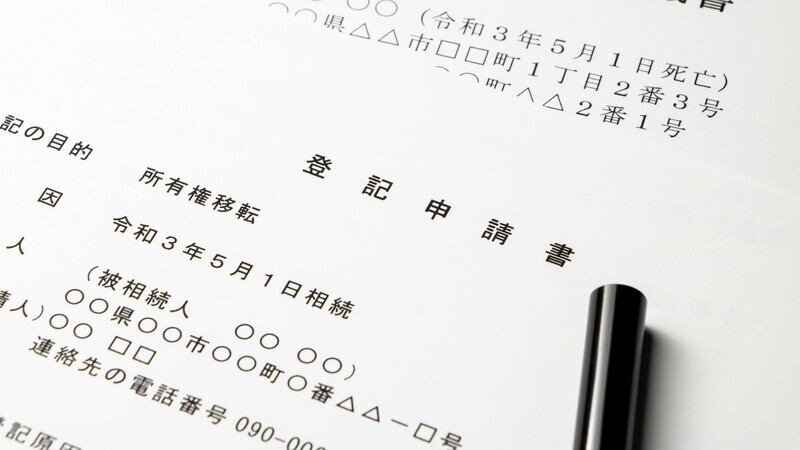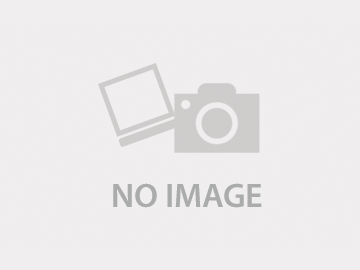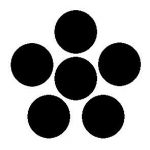令和6年4月から「相続登記」義務化へ…“施行前”に発生した相続も対象!登録免許税が「非課税」になる3つのケースとは?
相続登記における登録免許税についてチェック
相続登記における登録免許税とは、不動産を相続した人が相続登記をする際にかけられる税金のことです。
土地や建物も、評価額に1,000分の4をかけて算出します。たとえば、相続登記の対象となる土地が評価額1,000万円である場合は、4万円の登録免許税がかかります。
相続登記における登録免許税が免税されるようになった背景
登録免許税が免税されるようになった背景には、所有者不明土地問題が挙げられます。土地の所有者が死亡したあと相続登記をされず、そのまま長期にわたって放置されている土地が全国にはたくさんあります。
所有者不明のままでは土地利用ができません。公共工事や災害復興に支障が出たり、老朽化した建物が崩れる、ごみが処分できないなどで近隣に迷惑がかかることもあります。そのため、相続登記を促すことを目的として、相続登記を行う際の登録免許税に対して免税措置が設けられたというわけです。
相続登記における登録免許税が「非課税」(免税)になる3つのケース
相続登記はこれまで義務ではありませんでしたが、令和6年4月1日より義務化が決定しています。相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料が科されます。
施行前に発生した相続であっても対象です。そのため、免税期間内に登記することをおすすめします。
相続登記における登録免許税が非課税になるケースは、以下の3つです。
・評価額が100万円以下の土地を相続した場合
・土地を相続によって取得したが、登記をせずに死亡した場合
・土地の表題部所有者がすでに亡くなり、その相続人が所有権保存登記をする場合
それぞれ解説します。
評価額が100万円以下の土地を相続した場合
当初は、市街化区域以外かつ評価額10万円以下の土地に限り免税措置の対象でした。
ところが、令和4年の税制改正により市街化区域内の土地も対象となり、評価額も10万円から100万円に引き上げられたことで、より多くの土地への適用が可能となりました。
100万円以下の土地というとまだまだかなり限られてしまう現状はありますが、該当する場合は免税措置が適用されます。
土地を相続によって取得したが、登記をせずに死亡した場合
相続により土地を取得した人が相続登記をせずに死亡し、さらに相続が発生した場合にも適用されます。
主なケースとして、数次相続が発生している場合などが該当します。この場合、最初に発生した相続にかかる登録免許税に対してのみ免税措置が適用され、そのあとに発生した相続については免税になりません。

上記の事例で、たとえば土地の評価額が1,000万円だった場合の登録免許税は以下のとおりです。
土地所有者から妻と子に2分の1ずつ所有権移転(相続)登記する
→土地の評価額1,000万円×0.4%=4万円
妻の持分2分の1を子に所有権移転(相続)登記する
→土地の評価額1,000万円×0.4%=4万円
本来であれば、一次相続の際にかかる登録免許税4万円と、二次相続の際にかかる登録免許税4万円を合わせて8万円がかかります。
しかし、免税措置が適用されることで一次相続の際の登録免許税が免税されるため、二次相続の際の4万円のみがかかります。
土地の表題部所有者がすでに亡くなり、その相続人が所有権保存登記をする場合
土地の表題部所有者がすでに亡くなっており、その相続人が所有権保存登記をする場合も該当します。
登記簿(全部事項証明書)は、表題部と権利部の2段構造になっています。
現在であれば、表題登記のあと所有権保存登記に進むことが一般的であるため、長期にわたって権利部が未登記のままになることはあまりありません。しかし、中には表題部の登記のみで所有権保存登記がされていない土地も存在します。
表題部の所有者が死亡している場合、相続人名義での所有権保存登記が可能です。評価額が100万円以下であれば、その登記にかかる登録免許税に対して免税措置が適用されます。

以上、登録免許税が免税となる3つのケースを紹介しました。
相続登記における登録免許税の免税期間はなぜ延期されている?
相続登記における登録免許税の免税期間は、平成30年4月1日から令和7年3月31日までです。
登録免許税の免税期間は、当初は令和3年3月31日までの予定でしたが、以下のように延長されています。
理由としては、免税措置の適用前と比べ、相続登記の申請件数や筆数が増加していることが挙げられます。相続登記を促すための方策として十分効果を上げているといえる結果であり、今後も引き続き必要な措置であるとの判断から、このように繰り返し延長されています。
相続登記における登録免許税が非課税になるためには?
相続登記の申請書に決まった形式はなく、必要事項が正しく記載されていれば問題ありません。法務省のホームページなどから雛形をダウンロードして使用するのもよいでしょう。
申請書には、以下の事項を記載します。
・登記の目的
・登記原因
・被相続人の氏名
・相続人の氏名、住所、日中連絡のつく連絡先
・添付書類
・登記識別情報の通知を希望するかどうか
・申請日
・申請先の法務局
・課税価格、登録免許税
・不動産の表示
登記の目的
登記の目的を記載します。被相続人が対象の不動産を単独で所有している場合と、誰かと共有している場合とで、記載する文言は異なります。
・単独所有の場合:所有権移転
・共有の場合:〇〇持分全部移転(〇〇の部分は被相続人の氏名を記載します)
登記原因
相続を開始した日、つまり被相続人の死亡日を記載します。死亡後に取得した戸籍を確認し、そのとおりに記載します。死因が孤独死などで死亡日がはっきりしない場合も、戸籍の記載に従ってそのまま記載します。
被相続人の氏名
被相続人の氏名を正式名で記載します。戸籍のとおりに記載するとよいでしょう。
相続人の氏名、住所、日中連絡のつく連絡先
不動産を相続する人の氏名、住所、日中連絡のつく連絡先を記載しましょう。複数存在する場合は、それぞれの持分も記載します。
申請に不備があった場合は、記載した連絡先に法務局から連絡が入ります。連絡のつきやすい番号を記載しましょう。
添付書類
相続登記の際に添付する書類は、どういった方法で相続をするかによって異なります。
法定持分どおりに相続する場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、住所を表すもの
・相続人全員の戸籍、住所を表すもの
・評価証明書
被相続人の最後の住所と登記簿記載の住所が異なる場合は、それぞれ証明できるものが必要です。戸籍の返却を希望する場合は、相続関係説明図を添付します。法定相続情報証明制度を利用し、法定相続情報一覧図の写しを添付することで、戸籍の添付を省略できます。
遺産分割協議を行った場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、住所を表すもの
・相続人全員の戸籍、住所を表すもの
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・評価証明書
相続人全員の印鑑証明書は、被相続人の死亡日以降に取得されたものであれば、古いものでも問題ありません。
遺言書に従って相続する場合
・被相続人の死亡事項記載の戸籍
・受遺者の戸籍
・遺言書の正本または謄本
公正証書遺言以外で法務局で保管されていない場合は、家庭裁判所にて検認を受け、検認済みの証明文が付された遺言書でなければなりません。
また、遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の印鑑証明書など、ケースによってほかの書類も必要です。
登記識別情報の通知を希望するかどうか
登記識別情報とは、昔でいうところの権利書です。通知を希望しなければ発行はされません。管理が不安であるなどの事情がなければ、通知を希望してよいでしょう。
申請日
実際に申請する日を記載します。郵送による申請の場合は、申請書類一式をポストに投函した日で問題ありません。
申請先の法務局
申請人の住所地ではなく、対象の不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。不動産が複数あり、たとえば〇〇市に土地2筆、△△市にも土地2筆あるといった場合には、〇〇市を管轄する法務局と△△市を管轄する法務局それぞれに申請する必要があります。
課税価格、登録免許税
課税価格は、評価証明書に記載されている固定資産評価額をもとに記載します。そのままの金額ではなく、1,000円未満を切り捨てた金額です。
登録免許税については、免税措置の適用を受けて非課税にする際は、非課税となる根拠を登記申請書に記載する必要があります。
免税措置を受けるには、以下の文言を記入します。
・租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税
・租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
非課税となる根拠を記載しなければ、免税措置が適用されないことに注意が必要です。必ず記載するようにしましょう。
不動産の表示
相続の対象となる不動産の情報を記載します。全部事項証明書を取得し、そのとおりに記載すれば問題ありません。
相続登記の免税措置を受ける際の注意点
相続登記における登録免許税が非課税になる条件や、免税期間について解説しました。
所有者不明土地の問題解決のための免税措置であり、登録免許税の免税対象となるのは土地のみです。建物は対象にならないことに注意が必要です。
相続は非常に身近な問題であり、誰もが直面する可能性があります。仕組みや手続きが複雑で、登記申請はもちろんのこと、戸籍を揃えるだけでも一苦労です。
そのため、無理をせず専門家に依頼することを検討してみてください。相続についての相談は、相続診断士に相談するのがおすすめです。相続診断士から、ケースに合わせて行政書士や司法書士などの専門家に繋いでもらえるためスムーズに対応することができます。