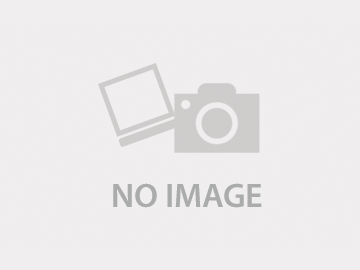「余命半年だったけれど、2年も生きている」腫瘍内科医が語る、医師宣告の余命宣告が当たる驚愕の確率 | ニコニコニュース
■最後までがんと闘うから最期に苦しんでしまう
がんに関して誤解をしていたり正しい知識がないせいで、必要以上に恐怖を感じたり絶望的になったりする人が多いように思います。そのようながんに関する誤解の一つに「緩和ケア」への誤解があります。
緩和ケアというと、治療が行き詰まった患者に対して行われる最後のケアのように受け取る人がまだまだ多くいます。しかし、緩和ケアは「治療か緩和ケアか」という二者択一のようなものではありませんし、もちろん死の宣告のようなものでもありません。
そうではなく、本来ならば積極的な治療(手術、放射線治療、抗がん剤治療)と並行して行うべきものです。このことは、がん対策推進基本計画にも「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が明記されています。
実際に、2010年には早期から緩和ケアを受けることが延命にもつながると「ニューイングランド/ジャーナル・オブ・メディシン」という世界で最も権威ある医学雑誌の一つで発表されました。手術が難しい進行性の肺がん患者に対して、抗がん剤治療のみを受けていたグループと、抗がん剤治療に加えて月に一度、外来で緩和ケアを受けたグループを比較したところ、緩和ケアを受けていたグループのほうが、生存期間が2.7カ月も延びたのです。
たった2.7カ月と思う人もいるかもしれませんが、世界初の免疫治療薬として承認され、「夢の新薬」と言われたオプジーボの肺がんに対する生存期間の延長が2.8カ月とされています。単純比較はできませんが、緩和ケアが抗がん剤と同じような治療効果をもたらす可能性があると示されたのは、非常に画期的なことです。この結果から考えれば、緩和ケアは手術、放射線治療、抗がん剤治療に続く第4の標準治療と言っても過言ではないのです。
では緩和ケアとは具体的に何をするか。もちろん、「症状を緩和すること」も大切ですが、がん治療と並行して行う緩和ケアでは、「信頼関係の構築」から始まり、「病状の理解」「治療の意思決定支援」「終末期の話し合い」なども大切とされています。これらのことは、「人生会議」と言って、人生の最後をどのように過ごしたいかを元気なうちに考えておこうというのが目的です。つまり、患者が自分の病状を適切に理解できるようサポートして、抗がん剤治療や緩和ケアなどの選択肢から適切に選べるように支援することが緩和ケアの役割なのです。
どこで亡くなるのが最もQOL(生活の質)が高かったかを遺族にアンケートした調査では、最もQOLが高いのは自宅、次が緩和ケア病棟、最も低いのが病院死という結果になりました。緩和ケア病棟に行くというともう何もしてもらえないと感じる人がいますが、苦痛を取り除いてQOLを大切にして過ごせる場所が緩和ケア病棟です。それにもかかわらず、日本ではいまだに病院死が最も多くなっています。これはがんの病状や緩和ケアに関する正しい知識が知られていないからです。
ほかにも知っておいてほしいこととして、脳卒中や心不全などの慢性疾患や認知症、老衰が右肩下がりで徐々に体の自由が利かなくなっていくのに対して、がんの患者は亡くなる直前までは普段とあまり変わらず過ごせるということが多いです。個人差はありますが、亡くなる1カ月くらい前までは比較的元気で、一旦症状が出ると、階段を転げ落ちるように全身状態が悪化していきます。それを知らないと、抗がん剤治療などの積極的治療で効果が得られなくなった時期が来た後も体は元気だから、治療の終了をなかなか受け入れられない。ゆえに、死ぬギリギリまで抗がん剤を使って非常に辛い思いをすることになるのです。医師から標準治療の終了を告げられても「自分はこんなに元気なのに、治療できないはずはない」と納得できず、最後の最後まで抗がん剤を使ってしまうのです。
標準治療が終了した後に抗がん剤を使用しても延命効果は期待できません。この時期に無理に抗がん剤を使うことは過剰医療につながり、不要な苦しみが増すだけです。標準治療が終了した後は、むしろ緩和ケアを受けたほうがQOLの向上や場合によっては延命効果が期待できます。この点を知らない患者が非常に多いのです。
抗がん剤の使用は本来、専門家である腫瘍内科医が行うべきです。しかし日本には腫瘍内科医の数が少なく、がんの治療は外科医が行うことが多くなっています。外科医は手術のプロですが、必ずしも抗がん剤のプロではありません。よって、「抗がん剤のやめ時」を正しく理解していないのです。
抗がん剤のやめ時を判断するのが難しい別の理由として、余命がわからないこともあります。よく、医師から「余命宣告を受けた」と言われますが、実は余命というのはせいぜい3分の1程度しか当たりません。つまり、医師だって人間がいつ死ぬかなどわからないのです。余命半年と言われたけれど1年も2年も生きる人がいるのはそのためです。あまり当たらないにもかかわらず、余命宣告を平気でするのはいかがなものかと私は思います。
それよりも重要なことは、病状を理解して予後について話し合うことです。患者は、どれほどがんが進行していても「自分には奇跡が起こって治る」と信じています。もちろん希望を持って前向きに過ごすことは重要ですが、病状に対する正しい理解がなければ、結果として過剰な抗がん剤によって体を痛めつけることになってしまうのです。
■標準治療に勝るものはないトンデモ医療に流されるな
がんに対する誤解は過剰診療を生むだけではなく、まったく効果のない「トンデモ医療」にだまされてしまう不幸な結果にもつながります。がんになったときに選択すべき最高の治療法は、保険適用された「標準治療」です。標準治療というと平凡な治療と思う人がいるかもしれませんが、それも大きな誤解です。標準治療こそが、世界中の医師が勧めるベストな治療法です。
なぜなら一つの治療法が保険適用されるまでには、効果があるかどうかが徹底的に調べ抜かれているからです。日本の医療費がこれほど増大して医療費抑制が命題になっている中、国が効果の不確かな治療法に公費を使うはずがありません。保険適用された標準治療は、厳しいプロセスを通過して選ばれた、言ってみればスーパーエリートの治療法と言えるのです。
私が多くの患者を診ていて最も悔しく感じるのは、本当ならば助かるはずの患者がトンデモ医療にだまされた結果、手遅れになってしまうことです。このような患者を見るたびに、トンデモ医療は医療という名を使った詐欺行為だと痛感します。なお、特に教育レベルや収入が高い人ほど怪しいがんの治療法にだまされやすいようです。
トンデモ医療を見分けるには、次の6つのポイントを押さえると良いと思います。①保険がきかず高額な治療法は危険、②「どのがんにも効きます」という文言を信用しない、③「免疫力アップ」という言葉にだまされない、④個人の経験がほかの人にも有効とは限らない、⑤細胞実験レベルのデータだけでは信用できない、⑥「がんの予防」に効果があるからといって「がん治療」にも効くわけではない。
がんと診断されたらショックでわらにもすがりたくなる気持ちはよくわかります。しかし、トンデモ医療にだまされてお金も健康も失うことのないよう、冷静に判断してください。
インフォームド・コンセントについては、日本でも定着してきているのですが、不適切な形でインフォームド・コンセントが行われている事例があります。不適切なインフォームド・コンセントの一例として、患者自身に責任を押しつける「自己責任押し付け型インフォームド・コンセント」があります。十分な説明がないにもかかわらず「効果が20%の抗がん剤A」「効果は30%だが副作用が強い抗がん剤B」「緩和ケア」といった選択肢だけが示されて、「どれにするか、次の診察までに決めてきてください」と患者に責任を押しつけるような形で行われるものです。どれにするかと言われても、患者は「選ぶことができない」というのが本音と思います。
■がんを潰し切るのではなく共存しながら長生きする
また、「見放し型インフォームド・コンセント」と言って、「あなたの標準治療は終了しました。もう治療はありません。ホスピスを勧めます。当院での診療は終診になります」と見放し、追い出そうとする例です。多くのがん専門病院や大学病院などでもこのようなインフォームド・コンセントの事例が見られます。このように言われてすぐに納得できるでしょうか。
最近では、世界的な動向としても、シェアード・ディシジョン・メイキング(共同意思決定)に基づくインフォームド・コンセントの重要性が求められてきています。つまり、患者と医師が十分にコミュニケーションを取り、患者の意向も含めながら、患者と共同して、意思決定をしていく方法です。このような患者に寄り添うようなインフォームド・コンセントが広まることを願っています。
今は、治すことが難しいがんであってもがんと共存できる時代になりました。がん治療の目標はステージごとに異なります。早期のがんは、しっかり治して再発させないことが目標です。そのため、エビデンスに基づいた標準治療を頑張って受けることが正解です。
一方で、再発したがんを治すことは簡単ではありません。再発がんの場合、重要なことはがんを治すことよりも、より良い日常を生きることになります。がん患者は頭の中ががんでいっぱいになります。どうすればこのがんから逃れることができるか、朝から晩までそのことばかり考えてしまいます。すると、がんに怯えて大切な時間を失ってしまうことになるのです。
そうならないために、再発進行がんの場合は、がんとより良く共存するという視点が重要です。私の患者で乳がんが全身に転移していながら、抗がん剤を使って夢だった世界一周を実現した人がいます。毎週のように海外へ行って、最終的には世界を3周も回ることができました。
もしも彼女が自分の病状を理解せずにトンデモ医療に何百万円も費やしていたら、世界一周は実現できなかったでしょう。病気を正しく理解して、病状によってはがんと共存するという選択肢を持つことで、より良い日常を過ごすこともできるのです。
※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年8月16日号)の一部を再編集したものです。
----------
腫瘍内科医
日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授、部長、外来化学療法室室長。1963年山梨県富士吉田市生まれ。富山医科薬科大学(現富山大学)医学部卒業後、国立がんセンター中央病院内科レジデント、内科スタッフ。2004年ハーバード大学生物統計学教室に短期留学、ダナファーバーがん研究所、ECOGデータセンターで研修を受ける。その後、国立がんセンター医長を経て、2011年より現職。あらゆる部位のがんを診られる「腫瘍内科」の立ち上げは、当時の日本では画期的であった。国内における臨床試験と抗がん剤治療のパイオニアの1人。2022年、医師主導webメディア「Lumedia(ルメディア)」を設立、スーパーバイザーを務める。日本臨床腫瘍学会指導医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医。著書に『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)などがある。
----------