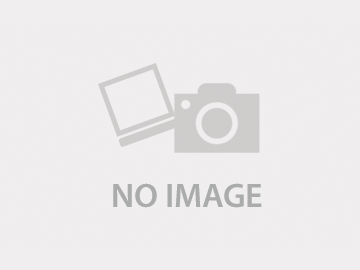懐かしの「折りたたみ式ケータイ」に乗り換える高校生が続出…ジワジワ広がる「スマホ疲れ」という本音 | ニコニコニュース
■アプリもGPSもタッチ画面もない
16和音のメロディーが届けた、新着メッセージ。心を躍らせ、小さなディスプレイで夢中になって返信をつづる。切手サイズの写メを送り合えば、粗い画像の向こう側にたしかなつながりを感じられた――。
1990年代から2000年代にかけて花開いた「ガラケー」文化がいま、アメリカで一部の若者の心をわしづかみにしている。
彼らが使う携帯には、アプリもGPSもタッチ画面もない。数字の並ぶキーパッドと、10文字も打てば折り返してしまう小さなディスプレイがすべてだ。必要なときには最小限の通話を行い、お世辞にも高画素とは言えないカメラで友人とのひとときを記念に収める。
惹(ひ)かれる理由はさまざまだ。ある青年は未知のガジェットとして新鮮味を見いだし、通知の嵐に辟易(へきえき)したある少女はガラケーに乗り換えて自分らしい時間を取り戻した。
不便なガジェットをあえて相棒に選ぶことで、外出すればリアルな街とのつながりが感じられ、自分自身の脳を使ってものを考えるようになったという声もある。
20年前の若者が未来を感じた折りたたみ式の電話は、2023年になっても同じように若者たちを魅了しているようだ。
こうした旧式携帯は、アメリカではフリップフォン(折りたたみ電話)などと呼ばれる。狭義のガラケーは日本仕様の製品を指すが、本稿では便宜上、アメリカのものも含めてガラケーと表記している。
■ガラケーを使う高校生クラブが立ち上がった
米ニューヨーク・ブルックリンに位置する広大なプロスペクト公園の片隅に、市民に愛される中央図書館が居を構える。図書館のホールへと続く石段が、「ラッダイト・クラブ」のメンバーたちの集合場所だ。
ニューヨーク・タイムズ紙は、スマホを使わないこの一風変わった高校生クラブの活動を報じている。
記事によると、日曜日になるとどこからともなくメンバーが現れ、図書館の石段へと集う。InstagramやSnapchatでグループチャットが届いたから来たわけではない。約束の時間に、約束の場所に集まったのだ。
メンバーの一人、高校3年生のオディール・カイザーさんは、同紙に語る。「晴れても降っても、たとえ雪の日であっても、毎週日曜日になると集まります。お互い連絡は取らないから、だからこそ来なくてはいけないんです」
メッセージ1通でドタキャンできない状況が、仲間への責任感と結束を生んでいる。
彼らは意図的にテクノロジーから距離を置いている。メンバーの一部はスマホではなく、あえてガラケーしか持たない。スマホを持っているメンバーも、集会中は目に付かない場所にしまっておく。
メンバーたちは落ち葉を踏みしめて丘をのぼり、混雑したパークのなかでも静かな一角に着くと、手頃な丸太を探してきて輪を作る。そのうえに腰掛け、思い思いの時間を過ごすのが通例だ。
スケッチをし、読書に興じ、あるいはただ風のリズムに耳を傾ける。この時間だけは、だれかのきらびやかな自撮りに「いいね」する必要もなければ、溜まったソシャゲ(オンラインゲーム)のライフを消費する必要もない。
■SNSで燃え尽きた17歳女性に起きた変化
ラッダイト・クラブの名は、10世紀にイギリスで起こった機械化反対運動に由来する。メンバーは文明を捨てたわけではないが、スマホとの距離を見直そうとしている。
メンバーで高校4年生のローラ・シュブさんは、ニューヨーク・タイムズ紙に対し、「折りたたみ携帯を手にした瞬間、すべてが変わりました」と語る。「脳を使い始めたんです。自分自身を人間として観察するようになりました」。本を書く余裕も生まれ、すでに十数ページを書き進めた。
クラブを立ち上げたのは、17歳のローガン・レーンさんだ。ソーシャルメディアに燃え尽きた彼女は、はじめにInstagramのアプリを削除し、ついには自身のiPhoneを箱にしまった。生まれた瞬間からこの世にスマホがあった彼女にとって、これが新しい扉を開いた。
「頭で考えるようになりました」と彼女は言う。iPhoneのない生活は、それまでとまったく違うものだった。図書館で小説を借り、地下鉄のグラフィティに目を奪われ、新しい友人たちと知り合った。
ブルーライトに悩まされず、目覚ましの力を借りることなく朝7時に起床するようになったという。iPhoneを運河に投げ捨てることまで夢想したが、さすがにそれは思いとどまった。
両親はおおむね満足している。夕食の席では、ローガンさんからその日の冒険物語を聞くことができるようになった。ただし、安全性だけは気がかりだ。スマホのように位置情報を把握できなくても、せめてガラケーだけは持って出掛けてほしいと、両親はローガンさんの説得を試みている。
最近、ローガンさんの母親は、スマートフォンでTwitterを使い始めた。そして案の定、早くもTwitter疲れに直面している。ローガンさんはニューヨーク・タイムズ紙に対し、「ちょっとだけ優越感をあじわえるので、この状況は気に入っています」と笑う。
■2007年から世界は大きく変わった
2007年を契機に、ガラケーがふつうだったそれまでの携帯業界は一変した。
同年1月9日、サンフランシスコのモスコーニセンターで開かれたApple製品の見本市、マックワールド。基調講演に登壇したスティーブ・ジョブズCEO(当時)は、大入りの観客にステージ上から笑顔を振りまき、こう語りかけた。
「ご来場ありがとう。われわれは今日、共に歴史の1ページを刻むことになる」
後世に残るほどに革新的な、3つの製品を発表するという。タッチスクリーン搭載のiPod、まったく新しい携帯電話、革命的なインターネットデバイスの3つだ。
壇上のスクリーンには3つを象徴するアイコンが映し出されたが、様子がおかしい。代わる代わる表示されるアイコンは次第に速度を増し、まるで互いに融合するかのようだ。
観客からどよめきが漏れると、自信のある製品を発表するときはいつもそうであるように、いたずらな笑みを浮かべながらジョブズは告げた。
「そろそろ気づいたかい? これらは3つの別々のデバイスではない、1つのデバイスだ。われわれはこれを、iPhoneと名付けた」
クパティーノの本社社屋で2年半をかけて秘密裏に開発されていたiPhoneが、世の中に解き放たれた瞬間だった。
■携帯電話のスタンダードになったiPhoneとAndroid
当時としては革命的だった全面スクリーンと、直感的なタッチ操作、そしてAppleならではの親しみやすいインターフェース。iPhoneの登場は、ガラケーを過去のものにした。
業界を牛耳るはずのAppleだったが、未来を見通すジョブズにとってさえ計算外だったのは、競合OSとなるAndroidの登場だ。Mac OS(現macOS)内部の検索機能を重視していたAppleは当時、取締役会にGoogleのエリック・シュミットCEO(当時)を迎えていた。
ジョブズはiPhoneが「他社のあらゆる携帯の5年先を行く」と豪語したが、その裏側を支える数々の研究開発の成果は、すべて敵の親玉に筒抜けだったのだ。
iPhone発表からわずか10カ月後にGoogleがAndroidを発表すると、iOSのリードは急速に縮小。ジョブズは激怒しシュミットを取締役会から追放したが、後の祭りだ。以来、両OSはシェアを二分しながら、世界にスマートフォンを浸透させてきた。
■スマホしか知らない世代にはレトロなアイテムに見える
こうしてスマホは携帯電話のスタンダードとなった。ところがいま、ガラケーを知らないアメリカの若者たちにとって、かえって旧式の機種が興味をかき立てている。
ソーシャルメディア疲れで距離を置きたい、通話だけできればいいという需要に応えるほか、レトロでファッショナブルなアイテムとしても注目されているようだ。
米CNNは、「Z世代がいま熱狂する最新の『ヴィンテージ』アイテムは、1990年代半ばにミレニアル世代のあいだで流行した、あの折りたたみ携帯である」と報じている。
ソーシャルメディアに気を散らされる心配がないだけでなく、まるで90年代の映画『マトリックス』に登場する「Nokia 8110」のようだとして、レトロな魅力を放っているようだ。
■乗り換えを勧めるインフルエンサーも
低画質のカメラが生み出す独特の風合いも新鮮に受け止められ、ガラケーのカメラでいかに美的な写真を撮るかを指南する動画もTikTokに登場している。
2台持ちで使い分ける若者もいる。CNNによると、イリノイ大学のある学生はスマホを持っているが、人と会うときにはあえてガラケーだけを持って行くという。人々の目を引き、新しい友人関係をつくるための絶好の会話の糸口になるようだ。
別の学生はCNNに対し、「折りたたみ携帯を持って出掛ける人々は増えていると思います」と語る。「楽しくてノスタルジックだし、率直に言って雰囲気がいいですから」
アメリカではいまでも新旧の機種が販売されており、手頃なものでは契約プランによって20ドル前後から手に入る。
米俳優のダヴ・キャメロンがガラケーに乗り換えたほか、TikTokのインフルエンサーのなかにも乗り換えを勧める人々が出てきた。
■画面越しでは見られない世界があると、若者たちは気が付いた
スマホの登場は世界を変えた。人々はいつも情報と接することができ、すきま時間を無駄にしなくても良くなった。移動中にニュースを確認し、仕事のメールに返信し、そして子供の居場所さえ手軽に確認できる。
だが、すきま時間を有効活用できる世界は、すきま時間が奪われた世界でもある。街の喧噪(けんそう)を感じながらただ歩いたり、電車に揺られながら車窓を眺めたりする時間は、ずいぶんとぜいたくなものになった。
スマホ越しにつながろうとするほど、心はすり減る。ガラケーならどうだろうか。連絡先交換を持ちかけられての「LINEやってないんです」は時として説得力に欠けるが、「ガラケーなんです」と取り出してみせれば角は立たないかもしれない。
ガラケー全盛期よりも少しばかり大きくなったスマホのディスプレイは、私たちからますます多くの時間をのみ込んでいっている。それと反比例するかのように、実世界への興味は驚くほど小さくなった。しじゅう画面越しの世界を眺める若者たちが、スマホ疲れに悩むのも無理はない。
スマホのない生活は、まるで別のゲームだ。空を見上げて雨が降るかを占い、道行く心温かい人々に場所を尋ねながら、自分が信じたルートで目的地へと向かう。スマホにぎっしりと詰め込まれた演算チップではなく、自分自身の脳で判断する人間らしい体験がそこにはある。
もちろん、現代社会を生きるすべての人々が実践可能な試みではないし、スマホの存在が悪というわけでも決してない。それでも、ガラケーひとつをポケットに突っ込んで街へ繰り出すニューヨークの若者たちは、ちょうど20年前には誰もがそうであったように、手探りで世界を生きるやり方に魅力を見いだしているようだ。
----------
フリーライター・翻訳者
1982年生まれ。関西学院大学を卒業後、都内IT企業でエンジニアとして活動。6年間の業界経験ののち、2010年から文筆業に転身。技術知識を生かした技術翻訳ほか、IT・国際情勢などニュース記事の執筆を手がける。ウェブサイト『ニューズウィーク日本版』などで執筆中。
----------