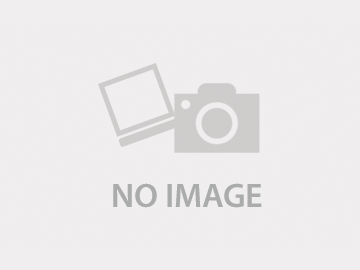「頼むから死んでくれ」から「よく頑張った」へ...。伝説の"御大"・島岡吉郎の凄みと人間味 | ニコニコニュース
![明治大学野球部総監督の島岡吉郎氏(1911~89)。同じ明大ラグビー部の北島忠治監督とともに名物監督として有名だった。愛称は「御大」(写真:共同通信)]()
明治大学野球部総監督の島岡吉郎氏(1911~89)。同じ明大ラグビー部の北島忠治監督とともに名物監督として有名だった。愛称は「御大」(写真:共同通信)
【連載②・松岡功祐80歳の野球バカ一代記】
九州学院から明治大学へ入学。そしてかの有名な島岡吉郎監督の薫陶を受け、社会人野球を経てプロ野球の世界へ飛び込んだ。11年間プレーした後はスコアラー、コーチ、スカウトなどを歴任、現在は佼成学園野球部コーチとしてノックバットを握るのが松岡功祐、この連載の主役である。
つねに第一線に立ち続け、"現役"として60年余にわたり日本野球を支え続けてきた「ミスター・ジャパニーズ・ベースボール」が、日本野球の表から裏まで語り、勝利や栄冠の陰に隠れた真実を掘り下げていく本連載。第ニ回は前回の第一回に引き続き、松岡が飛び込んだ60年代の明治大学野球部のお話。伝説の名将・島岡監督による、現代ではあり得ない暴力的なシゴキの毎日と、それでも憎めない人間・島岡吉郎の深い魅力を振り返る。
■島岡監督の鉄拳を見て明治進学を後悔
噂には聞いていたが、明治大学野球部の厳しさは高校時代の比ではなかった。1911年生まれの島岡はまだ50歳、血気盛んだった。
「高校時代に"ケツバット"を食らうことはありましたが、監督に『殺してやる~』とまで言われたことはそれまでにありませんでしたから。
僕たち1年生は最初、グラウンドには入れない。シートノックが始まって、イレギュラーバウンドしたボールを野手が弾いた瞬間、外野まで競歩みたいに歩いていってパッカン、パッカンやる。『なんていうところに入ったんだろう』と思いました」
監督が鉄拳を振るのは日常茶飯、選手たちは反骨心を隠しながらひたすら耐えていた。
「島岡さんが一度興奮したら、誰が何を言っても止まらない。目が血走って、声がぱんと裏返るんですよ。『おい、●●!!』と始まったらもう終わり。目のまわりの筋肉がピクピクピクして......。怒りが収まるまで待つしかない」
時は1961(昭和36年)年――家庭でも学校でも暴力が当たり前の、ムチャクチャな時代だった。背番号3のユニフォームを着た長嶋が後楽園球場を駆け回っていた頃、松岡は絶望の淵にいた。
「御大が怒り始めたら、嵐が過ぎるのを黙って待つ4年生。その姿を見て『この人たちはどうやって過ごしてきたんだろう』と思いました。その精神力に驚くばかりで」
監督も厳しければ、上級生の指導も苛烈だった。
「何かミスがあれば、『1年生、集合!』ですからね。毎日、熊本に帰りたいと思うばかりで、ため息しか出ない。ボール拾いと、ダービー競争だけの日々でした」
100人以上いた1年生は、毎日、グラウンドを走らされる。上位でゴールすれば抜けられるが、足の遅い部員はまたもう1周、延々と走らされることになる。
「何十周も走るやつがいましたね。僕なんかは速かったから1周、2周で終わったけど」
部員は少しずつ減っていき、同学年で最後まで残ったのは14人。野球の技量以前の戦いに勝たなければならなかった。
■神宮デビューの試合で痛恨の大エラー
1961年春の東京六大学リーグ戦で明治大学は優勝を飾ったが、1年生の松岡はベンチ外だった。ようやくチャンスをつかんだのが翌春のこと。開幕の慶應義塾大学戦でスターティングラインナップに名を連ねた。
「8回表まで、僕が守るショートには一度も打球が飛んでこなかった。1アウト満塁のピンチで詰まったゴロが転がってきてから、ダッシュして捕って投げたら悪送球......。僕は投げた瞬間にしゃがみ込みました。そのプレーで2失点したあとに2点を追加され0対4で負けました」
当時、東京六大学の試合はNHKで全国放送される人気コンテンツだった。当然、デビュー戦における松岡の大失敗は、地元・熊本でも流された。
「親戚が集まって、テレビを見ていたそうです。僕がエラーをして、みんなが泣いたと聞きました。チームメイトは全員、『松岡は終わった』と思ったようです」

1961年春の東京六大学野球にて明大が通算13度目の優勝。ナインに胴上げされる島岡監督(写真:共同通信)
練習中のミスでも怒りまくる島岡監督が、宿敵である慶應に敗れるタイムリーエラーを犯した選手を許すはずがない。
「合宿所に戻ってから、ムチャクチャ怒られました。いや、怒られたなんてもんじゃなかった......さんざんやられたあと、最後に『松岡、頼むから死んでくれ』と言われました。『殺してやる』と責められた選手はたくさんいますが、島岡さんにそんなことを言われたのは僕だけじゃないですか」
もちろん、レギュラーポジションははく奪され、ベンチからも外れることになった。野球選手としては命を失ったのに等しい。
慶應との第2戦。松岡は明治神宮球場の外野席にいた。
「学生服を着て、切符切りをしていました。ぼーっと試合を眺めていると、肩を叩く人がいる。兄貴でした。僕のミスをテレビで見て、すぐに東京まで飛行機に乗ってきてくれたんですね。そして、『絶対にやめるなよ』と言い残して、帰りました」
多くを語らなくても兄の気持ちを伝わった。松岡はすぐに気持ちを入れ替えた。
「僕も『もう終わったな......』と落ち込んでいましたが、そんなことはしていられないと気
持ちを奮い立たせました。翌日から朝5時に起きて、坂道ダッシュを毎日やりました」
■毎日の坂道ダッシュで再びレギュラーに
1年後、松岡にチャンスが巡ってくる。
「3年春からベンチに入り、秋から試合で使ってもらいました。それは、近所の駄菓子屋のおばさんが毎日走っている僕を見ていて、島岡御大に助言してくれたから。5、6年経ってから、助監督に聞きました。『おまえの顔なんか見たくない』と島岡さんに言われた僕には、アピールするつもりはなかった。何の計算もありませんでした」
雨が降っても雪の日でも、松岡は早朝5時の坂道ダッシュを欠かさなかった。
「あの練習のおかげで、僕に根性がついたんです。体も小さいし、たいした選手じゃなかったんですけど、坂道ダッシュのおかげでプロ野球選手になれました」
高校時代に三塁手だった松岡をショートにコンバートしたのは島岡だった。タイムリーエラーでユニフォームを脱がしたのも、グラウンドに戻したのも島岡だった。
「おばちゃんにはいつも『頑張んなさいよ』と言われていましたけど、島岡さんに直接話をしてくれたとは想像もしませんでした。人生って、誰がどこで見ているかわかりませんね。それ以上に、駄菓子屋のおばちゃんの言葉に耳を傾ける御大はすごいなと思いました」
「法政大学の長池徳治(元阪急ブレーブス)と首位打者争いをして敗れたんですけど、初めてベストナインに選ばれました。その発表があった日、島岡さんの部屋に呼ばれました。おでんにビールと日本酒が一合置いてあって、『松岡、食べろ』と言う。『俺の目は節穴じゃなかった』という言葉を聞いて、僕は泣きました。その時だけは『よく頑張った』と言ってもらいました」
教え子たちが語る島岡伝説は、書籍でも、YouTubeでも知ることができる。暴力的で厳しくて、勝利に対する並外れた執念を持つ監督だった。
「たしかに、日本刀は押入れの中にありましたよ。それを選手たちの前で抜いて『殺してやる!』と言ったという話を聞いたことがあります。もちろん、演技でしょうけど。選手がみんな、腰を抜かしたと聞きました。何をするのでも過剰な方でした」
島岡には野球選手として誇れる実績はない。だからこそ、独特の表現で選手たちに指導を行った。
「誰かがバントをミスした時には自分の目をバンバン突きながら、『バントは目でやるんだ!』と言う。それを見た選手たちは震えますよ、迫力がすごすぎて。
ものすごく怖いんだけど、憎めない。選手との食事会で童謡を歌ってみたり、お化けが怖いから夜中にひとりではトイレに行けなかったり(笑)。かわいいところもあるんです。そういう方でした」
明治大学の4年間で島岡御大の薫陶を受けた松岡は、社会人野球のサッポロビールに進む。
「2年後にドラフト会議の記事を見た先輩が『松岡と同姓同名の選手がいるんだな』と驚いたそうです」
2年後、ドラフト1位でプロ野球に飛び込むことになるとは、当の本人も想像もしていなかった。
第3回へつづく。次回配信は2024年1月13日(土)を予定しております。
■松岡功祐(まつおかこうすけ)
1943年、熊本県生まれ。三冠王・村上宗隆の母校である九州学院高から明治大、社会人野球のサッポロビールを経て、1966年ドラフト会議で大洋ホエールズから1位指名を受けプロ野球入り。11年間プレーしたのち、1977年に現役引退(通算800試合出場、358安打、通算打率.229)。その後、大洋のスコアラー、コーチをつとめたあと、1990年にスカウト転身。2007年に横浜退団後は、中国の天津ライオンズ、明治大学、中日ドラゴンズでコーチを続け、明大時代の4年間で20人の選手をプロ野球に送り出した(ドラフト1位が5人)。中日時代には選手寮・昇竜館の館長もつとめた。独立リーグの熊本サラマンダーズ総合コーチを経て、80歳になった今も佼成学園野球部コーチとしてノックバットを振っている
取材・文/元永知宏